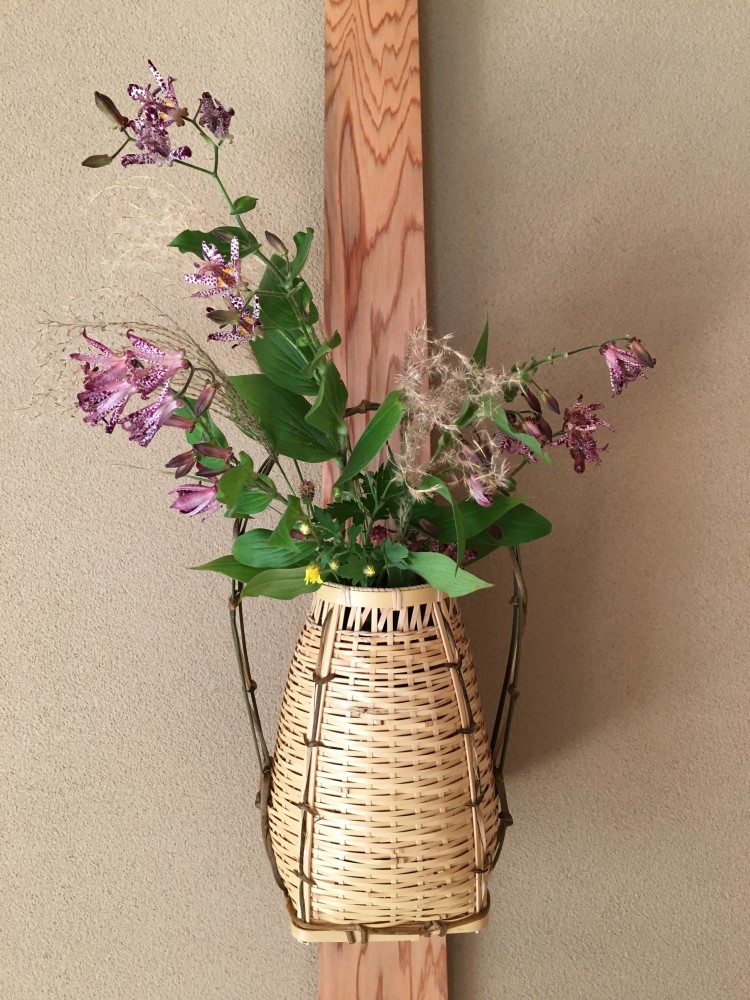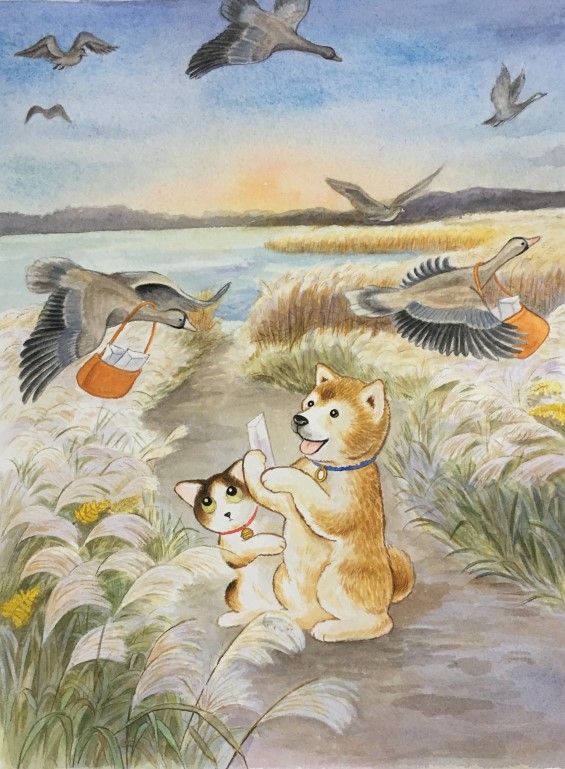11月になると、風炉から炉に変ります。
「炉開き」です。「茶人の正月」ともいわれます。

茶道では「炭手前」があり、お客様の前で炭を入れる所作を学びます。今の暮らしで、炭を使って火をおこす、ということは普通はないことと思います。茶道ならではの醍醐味と思います。
こちらは、「下火」を入れたところ。これにさらに大きな炉の炭をついでいきます。

炭は橡などの茶道専用につくられた炭を用います。これを火箸で掴んで美しく入れるのですが、箸使いが難しく・・・しっかり持たないと落としてしまうのです。
炉の炭は大きく、重いのです。
白鳥の香合の中には練香が入っていて、炉の中に入れ薫らせます。お香も風炉は爽やかな香りの香木、炉は深みのある練香、というように季節で変わります。

こちらの白く細い炭は枝炭といいます。しっかりつかむのは難しいです。

釜をかけました。練香の香りがゆっくり漂ってきます。
冬の午後の日差しは室内に長く入り、木々の影を畳にゆらゆらと作ります。

赤々と燃え盛っている炉の中です。
冬の茶室の美しい景色です。